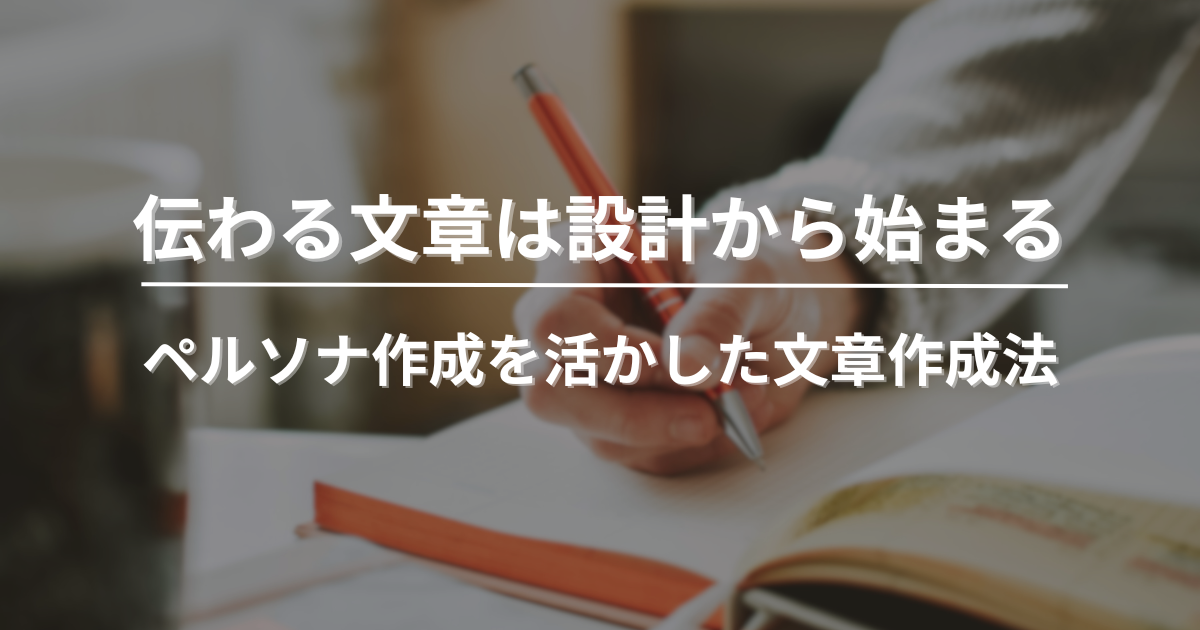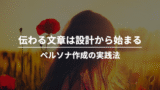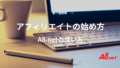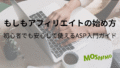ブログを書きはじめたばかりの頃、
「何を書けばいいかわからない」
「書きたいことはあるのに、手が止まる」
そんな迷いにぶつかったことはないでしょうか。
私自身、これまで制作会社で多くのコンテンツ制作に関わってきました。
現在は採用領域の仕事にも携わっており、求人原稿や採用サイトの設計にも日々向き合っています。
分野は違っても、どちらの現場でも共通して感じているのが、“相手が見えていないと伝わらない”ということです。
誰に届けるのか。どんな状況で、どんな悩みを抱えているのか。
――そこが曖昧なままだと、言葉はなかなか定まりません。
そしてそれは、ブログでも同じです。
むしろ、ひとりで書くブログだからこそ、「誰に向けて書くか」を意識することが、ブレない軸になってくれる。
この記事では、「ターゲット」と「ペルソナ」の違いから始めて、
実務とブログの両面での経験を交えながら、
無理なく自然にペルソナを描くための考え方をまとめていきます。
「書けない」が少しでも軽くなって、
あなたが言いたいことを“届けたい相手”に伝えられるようになる――
そんなきっかけになればうれしいです。
ターゲットとペルソナは、同じじゃない
ブログを始めると、よく「ターゲットを明確にしましょう」と言われます。
確かに、誰に向けて書くのかを意識することは、発信の軸を整えるうえで欠かせません。
ですが、そこで一緒に語られることが多い「ペルソナ」という言葉。
この2つを同じものとして扱ってしまうと、どこかで「言葉が響かない」「構成が定まらない」といったズレが生まれます。
ターゲット=まとまり、ペルソナ=たった一人
ターゲットとは、年齢・性別・職業などの属性で切り分けられた“まとまり”を指します。
たとえば、「30代の会社員」「副業に関心のある男性」など、一定の共通項を持つ層です。
一方、ペルソナはその中から想定する“たった一人の人物像”。
名前やライフスタイル、悩みまで具体的に描き出していきます。
どちらもマーケティングの中では使われる考え方ですが、
ブログのような“個人の発信”では、ペルソナの方が言葉を選ぶ軸になりやすいと感じています。
制作と採用、両方の現場で感じた「言葉の届き方」
制作会社にいたころ、よくあったのが「ターゲットは合っているのに、ページが響かない」というケースでした。
その原因をたどっていくと、どんな人が、どんなタイミングで、どんな気持ちで読むかまで考えられていないことがほとんどでした。
いま関わっている採用領域でも、まったく同じことが起きています。
「30代の現場職希望者」といったターゲットを設定しても、具体的な採用ペルソナ(どんな人に、どんな表現で届くか)を見直すだけで、反応が大きく変わることがあります。
実際に、ある求人原稿ではペルソナを設計し直したことで、
応募がそれまでの5倍近くに増えたこともありました。
届ける相手を“ぼんやりした層”ではなく、“顔の見える一人”に変えるだけで、成果も言葉の質も大きく変わる。
それは、ブログでも例外ではありません。
ペルソナは“理想の一人”でいい

ブログを書いていて、「言いたいことはあるのに、なぜか書きづらい」と感じることがありました。
頭の中では伝えたいことが浮かんでいるのに、構成が定まらなかったり、言葉が噛み合わなかったり。
そんな違和感の原因を見直したとき、
「誰に向けて書いているのか」が曖昧なまま進めていたことに気づきました。
制作や採用の現場では、自然とペルソナを立ててから言葉を考えていたのに、
自分のブログになると、つい感覚だけで進めてしまっていたのかもしれません。
ずっと大切にしてきたはずのことを、どこかで忘れていた感覚がありました。
ペルソナというと、少し堅く聞こえるかもしれませんが、
完璧な人物像を作りこむ必要はありません。
届けたいと思える“たった一人”が思い浮かぶだけで、言葉の輪郭は自然と整っていきます。
曖昧なまま書くより、“この人のために”と考える方が書きやすい
たとえば、「副業を始めたい人に向けて書こう」と考えても、
その人の生活や悩みが具体的に見えていなければ、
内容はどうしても一般的で、広く浅いものになりがちです。
でも、「夜の30分だけが自分の時間。何かを始めたいけれど、何から手をつければいいか分からず立ち止まっている人」
そんな一人を思い浮かべるだけで、伝える順番や言葉の選び方は自然と変わってきます。
書く手が止まりそうなとき、
「この人に届けるつもりで書く」という視点を持つだけで、文章の輪郭がはっきりしてくる感覚があります。
実務での経験が教えてくれた、“一人を思い浮かべる力”
制作の現場では、誰に届けるかを先に決めておくことで、
構成や言葉選びに迷いがなくなっていく感覚がありました。
どんな順番で伝えるか。どこまで説明するか。
その判断軸になるのが、思い描いた“たった一人”の存在です。
採用原稿でも同じで、
「30代・未経験歓迎」といった広いターゲットでは反応が薄かった求人が、
どんな生活をしていて、何に不安を抱え、どんな言葉に背中を押されるか――
そうしたペルソナを描き直したことで、応募が5倍近くに増えたケースもありました。
誰か一人を想定して書く。
それだけで、言葉は届きやすくなる。
ブログにも、この感覚はそのまま活かせると感じています。
実在しなくても、届けたい相手が浮かぶだけでいい
ペルソナは、実在の人物である必要はありません。
少し前の自分でもいいし、過去に関わった誰かをベースにしてもいい。
重要なのは、「この人に読んでほしい」「この人に届けたい」と思える対象が、書き手の中にあることです。
実在にこだわらず、自然に思い浮かぶ“ひとり”がいれば、それで十分です。
無理に作りこまずとも、
「この人がこの記事にたどり着いたとき、どう感じるか」を想像するだけで、言葉は前に進んでいきます。
細かく描けるほど、言葉に迷いがなくなる
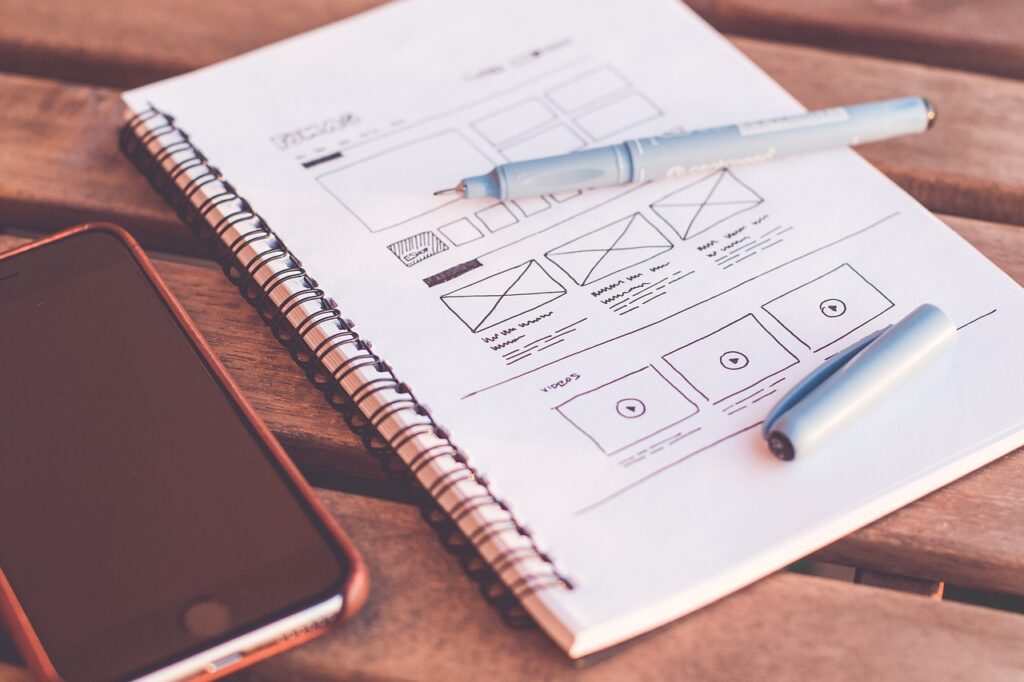
ブログを書くとき、何より最初に意識したいのは「誰に届けるか」だと感じています。 構成や文章の流れに悩んでいたときも、ここがはっきりすると一気に整理が進むことが多くありました。
「誰に向けて書くか」は、つい後回しにされがちだけれど、意外と大きな分かれ道になります。 それだけに、あえて“細かく描く”ことに時間をかける意味は大きいと考えています。
想像ではなく、設計する
よく「想像できる読者がいれば書ける」と言われますが、私自身はそうは思っていません。 何となく浮かぶ人では、構成も言葉もブレてしまう。
大切なのは、「どんな人に届けたいか」を明確にしたうえで、 その人がどんな暮らしをしていて、何を気にしていて、どこにひっかかりを感じているかを具体的に描くこと。 それが、書くための軸になります。
これは制作でも、採用でも、ブログでも変わらない感覚です。
ペルソナは“届けたい一人”を描くための道具
ペルソナを考えるとき、最初から完璧に描こうとする必要はありません。 ただ、「この人に届けたい」という意志があるなら、その人がどういう人物かを考えておく価値はあります。
以下は、実際に自分が描いたペルソナの一例です。
| 項目 | 記入例(イメージ) |
|---|---|
| 名前(仮名) | 佐藤 由美さん |
| 年齢・性別 | 37歳・女性 |
| 家族構成 | 夫と小学生の娘との3人暮らし |
| 職業・働き方 | 事務パート勤務(週5日、9:00〜15:00) |
| 世帯収入 | 月収約35万円(夫30万+自身5万) |
| ライフスタイル | 家事と育児の合間にスマホで情報収集。夜は家族が寝たあとに一息つく時間がある |
| 副業経験 | なし(ブログに興味はあるが、一歩踏み出せていない) |
| 使える時間 | 平日夜と週末。まとまった時間は取りにくく、1日30分が限界 |
| 趣味 | コーヒー、読書、スマホでインテリア画像を見る |
| 性格・価値観 | 慎重派。やるならちゃんとやりたい。でも失敗は避けたい |
| 悩み・不安 | 自信がない。途中でやめてしまうのがこわい。家族に相談しにくい |
| 行動のきっかけ | 教育費や将来への不安で「副業 ブログ」と検索 |
こうして書き出してみると、「どんな順番で話すべきか」「どこまで掘り下げるべきか」など、判断がぐっとしやすくなります。
完璧じゃなくていい、でも「ぼんやり」はもっとよくない
もちろん、すべての項目を埋める必要はありません。 ただ、あいまいなまま書き始めると、途中で何度も迷い、手が止まりやすくなる。
「何を描けばいいかわからない」というときこそ、自分が迷いやすいポイントを基準に、必要な項目だけでも具体化してみる。 そうすることで、構成にも言葉にも、一本の軸が通るようになっていきます。
ペルソナは、文章の見た目を整えるためのものではなく、 “伝える相手の姿をはっきりさせるための道具”として使う。 そう捉えておくと、無理なく続けやすくなります。
次章では、こうして描いたペルソナを、実際の文章にどう活かしていくかを見ていきます。
描いたペルソナを文章に活かす方法

ペルソナを描いてみた。名前もつけたし、生活や価値観まで整理した。
──なのに、いざ文章に向き合ってみると、言葉がしっくりこない。
「この人に届けたい」はずなのに、
気づけば“自分の伝えたいこと”ばかりになっていた。
これは、私自身が何度も経験してきた“ズレ”でした。
この章では、描いたペルソナをどう文章に活かすか──
「ちゃんと設計したのに、なんで伝わらない?」をなくすためのヒントを整理していきます。
構成は“生活の流れ”に合わせて組み立てる
たとえば、佐藤由美さんがブログを読むのは、夜、家事と育児を終えてようやくひと息つける時間。 そんなときに「収益化するにはSEOが…」といった話から入っても、なかなか頭に入ってきません。
だからこそ、冒頭ではまず「わかるよ、その不安」と共感し、 「大丈夫。ちゃんと進める方法もあるよ」と安心を届ける。
そのうえで、やるべきことや手順を整理して伝えていく──。 構成は、情報の順序というよりも、 その人の1日の流れと気持ちの変化に沿って組み立てることが大切だと考えています。
言葉選びは「口ぐせ」と「ためらい」に合わせる
佐藤さんのように、「やるならちゃんと」「でも失敗は避けたい」と考える人にとって、 「誰でもできます」「いますぐ始めましょう」といった断定的な言葉は、逆にプレッシャーになります。
「不安があっても大丈夫」「小さく始めて、少しずつでも進めていけますよ」といった、 背中を押すトーンのほうが、結果的に読まれやすくなると感じています。
その人がどんなことにひっかかりを感じ、どんな言葉を選びそうか。 「口ぐせ」や「ためらい」の感覚に寄せていくことで、伝わり方が大きく変わります。
言葉は、ただ届くだけではなく、行動のスイッチになることもあります。 読んだその人が「動けるかどうか」は、内容よりも“いまの気持ち”に合っているかどうか。 ためらいと前向きさ、そのバランスに寄り添う言葉選びが大切です。
一文一文に“届け先”を意識する
たとえば、 「副業は誰でも始められます」と書くと、 佐藤さんのような人には、少し無責任に感じられてしまうかもしれません。
それよりも、 「私も最初は不安でした。でも、少しずつできることが増えていくと、自然と気持ちも前向きになってきます」 といった書き方の方が、共感が生まれやすくなります。
書きながら、「この一文は、あの人に届くだろうか?」と問いかける。 ペルソナに話しかけるように書くことで、文章が抽象から具体へと変わっていきます。
ちなみに、描いたペルソナはそのままにせず、 記事ごとに「誰に向けて書くか」をひとこと添えておくと、軸がブレにくくなります。
Notionなど、ふだん使っているメモアプリにストックしておけば、思考の補助線として自然に活用できます。
ペルソナを“読む相手”として活かす
ペルソナは、設計図であると同時に、感情を込める相手でもあります。
書き出してみて、言葉に詰まったとき。 「この伝え方で合っているのかな?」と迷ったとき。
そんなときに何度でも立ち返る、“問いかけの相手”として、ペルソナは機能します。
「この人に届くかどうか」を問いながら書いていると、 次第に“読者”ではなく“あの人”のために書いている感覚が育ってきます。
それが、書き手としての視点を育て、ブレない軸につながっていきます。
次章では、こうして描き、言葉を選んだ結果が、 どのように文章全体に反映されていくのかを見ていきます。んだ結果が、 どのように文章全体に反映されていくのかを見ていきます。
まとめ|伝わる文章は、設計から始まる
文章がうまく書けないとき、私たちはつい「もっと上手に伝えなきゃ」と考えがちです。
でも、実際に見直すべきなのは、“書き方”ではなく“書く前の整理”かもしれません。
この前編では、文章を届けるための「設計」に焦点を当ててきました。
- 誰に伝えたいのか(ペルソナ)
- どんな状態の人か(気持ち・生活)
- どんな変化を促したいのか(ゴール)
この3つが定まると、言葉の選び方や構成の組み立て方が変わってきます。
それまでは「伝えたいことが多すぎて書けない」と感じていた人も、自然と迷いが減っていくはずです。
もちろん、完璧な設計図を最初から描く必要はありません。
ペルソナだって最初は“想像”から始まって構いません。
でも、「こんな人に届けたい」と想いを向けること。
その意識があるかどうかで、言葉の重なり方は大きく変わっていきます。
T-signでは、書く技術よりも、“届ける相手を意識する視点”を何より大切にしています。
「自分のために書いた記事」ではなく、「あの人に届く記事」へ。
その第一歩として、今回ご紹介した「文章設計」の考え方が、少しでもお役に立てば幸いです。
次回は、「設計をどう形にするか?」──文章の構成や流れの作り方についてお話しします。
構成が整えば、書くスピードも、伝わりやすさも、ぐっと変わってきます。
書くことに不安がある方こそ、ぜひ続きも読んでみてください。
著者プロフィール

副業ブログ運営者のT-signです。
普段は会社員として働きながら、副業ブログに取り組んでいます。
もともと、「副業って特別な人だけのもの」と思っていましたが、
小さな一歩を踏み出したことで、少しずつ未来が変わり始めています。
このブログでは、
副業初心者でも無理なく始められる情報を中心に、
「焦らず、無理せず、小さく積み上げる」スタイルで発信しています。
一緒に、小さな一歩を積み重ねていきましょう。