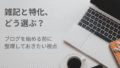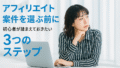ブログを立ち上げようとしたとき、意外と悩むのが“ドメイン名”。
かっこよくしたい、意味を持たせたい、でも何が正解か分からない──。
時間をかけて考えても、結局「これでいいのかな…」と不安になることもあります。
実際、ドメインはあとから簡単に変えられず、ブログの“住所”として長く使うもの。
だからこそ、最初の一歩として慎重になってしまうのは自然なことだと思います。
この記事では、ドメインを選ぶ際に意識しておきたい5つの視点を、
実体験も交えながらまとめています。
「まだ決めきれない」と感じている方の、ひとつの判断軸になれば幸いです。
ドメインを決めるときに意識したい5つの視点
ドメイン名は、たったひとつの文字列でありながら、
ブログの印象や信頼感、そして“育てていく感覚”にまで影響することがあります。
短くてシンプルな名前がよいのか、意味や想いを込めた名前がいいのか。
一度決めたら変えにくいだけに、慎重になる方も多いはずです。
ここでは、実際に選ぶときに考えておきたい視点を5つに絞ってご紹介します。
すべてを満たす必要はありませんが、何を優先するかの判断材料としてお役立てください。
1. 覚えやすく、打ちやすいか
どんなに素敵な意味を込めても、それが伝わらなければドメインとしては少しもったいない。
覚えにくい・入力しづらい文字列は、ブログの認知や再訪にも影響してきます。
たとえば、
- 長くて複雑な英単語が並ぶドメイン(例:myfabulousfreelancejourney.com)
- ローマ字読みと英語表記が一致しない(例:syain-blog → shain-blog?)
- ハイフンや数字が複数入っている(例:my-blog-2024-info.net)
こうしたものは、本人にとっては意味のある名前でも、他人には伝わりにくく、検索し直すハードルが上がってしまうことがあります。
反対に、
- 口に出してすぐ書ける
- 一度見れば覚えられる
- 打ち間違いが起こりにくい
そんなドメインであれば、特別なSEO対策をしなくても、自然とリピートされるきっかけになります。
ブログの初期段階では検索流入だけでなく、「URLを直接入力する」「名刺やプロフィールで見かける」といったアナログな場面も想定されます。
だからこそ、“使われるドメイン”としての設計を意識しておくと、あとでじわじわ効いてくるかもしれません。
2. ブログの内容や方向性と合っているか
ドメインは、ブログのテーマや内容に直結する必要はありません。
けれども、「何について書いているか」がある程度想像できる名前には、やはり一定の安心感があります。
たとえば…
- 「money-hacks.jp」なら、お金や節約・投資に関する内容を想像できますし、
- 「lifelog365.com」なら、日々の記録やライフスタイル系の内容が連想されます。
こういったキーワード型のドメインは、初めてブログに訪れる読者にとっても、ある種の“予告”になります。
特化型ブログとの相性が良く、SEO上のメリットがあると語られることもあります(※ただし現在では検索順位への影響は限定的とも言われています)。
一方で、「これからどういう記事を書いていくかがまだはっきりしていない」場合や、雑記的に幅広く書いていくつもりであれば、あえて意味を限定しすぎないドメインを選ぶのも十分アリです。
実際に運営していくなかで方向性が変わることは珍しくありません。
そのときに、テーマに縛られたドメインだと、**「名前と中身が合わない気がして書きにくくなる」**といった声も見かけます。
ブログの名前に、自分の意志を縛られないようにする。
それもひとつの選び方だと思います。
大切なのは、「いま書こうとしているテーマ」と「これから書くかもしれないテーマ」、その両方に違和感がないかを一度立ち止まって考えてみること。
完璧に合致させる必要はありませんが、続けやすさの土台になる視点として、見落としたくないポイントです。
3. ブランディングとしての意味があるか
ブログのドメインは、ただの“記号”ではありません。
名前の印象や語感は、想像以上にそのサイトの空気感や信頼度に影響を与えます。
たとえば:
- 自分の名前やニックネームをそのまま使ったもの(例:nao-blog.com)
- コンセプトを反映した言葉を組み合わせたもの(例:lifemap.jp)
- オリジナルの造語や短縮語(例:livma.jp = life + map)
こうしたドメインは、シンプルで記憶にも残りやすく、
SNSでの発信や名刺・プロフィールなど他の媒体と一貫性を持たせやすいという利点があります。
一方で注意したいのが、意味が強すぎる/わかりにくすぎるケースです。
- 読み方と綴りが一致しない
- 意味は深いけど、見ただけでは伝わらない
- カタカナや難解な英語で連想されにくい
こうした名前は、初見の読者にとっては記憶に残りにくく、
検索やシェアで不利になる可能性もあります。
「想いを込めた名前」と「他人に伝わる名前」は、必ずしも一致しません。
両立できないときは、伝わりやすさに少し寄せてみると、結果的に続けやすくなることもあります。
特別な意味がなくても、使いやすさ・覚えやすさ・言いやすさを意識しておくと、
ブログ全体に一貫した印象が生まれます。
4. ドメインの種類(.com / .net など)は適切か
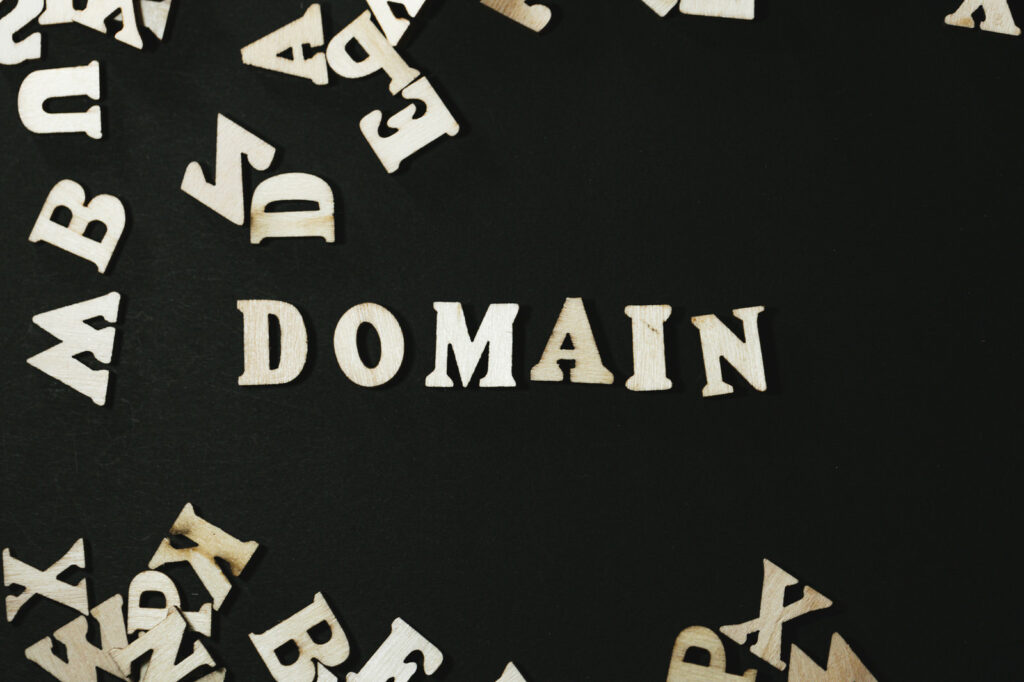
ドメインを選ぶとき、「末尾」にも注目しておくことが大切です。.com や .net のような定番から、 .xyz や .blog のような新しいもの、.co.jp のように法人に限定されたものまで、選択肢は年々広がっています。
それぞれの特徴と注意点を整理しておきましょう。
定番の「.com」や「.net」:見慣れていて安心感がある
- インターネット黎明期から使われている汎用ドメイン(gTLD)
- 多くの人にとって馴染みがあり、クリック時の警戒心も少ない
- 取得も簡単で、個人ブログでも無難に使える選択肢
新しいドメイン(新gTLD):デザイン性・意味性は高いが注意も必要
近年は、ICANN(国際機関)によって新たな汎用ドメイン(新gTLD:New Generic Top-Level Domain)が多く登場しています。
たとえば:
| ドメイン | 特徴 |
|---|---|
.xyz | Google親会社が採用。自由な印象で短くできる |
.blog | ブログ用途が一目で伝わる |
.tokyo | 地域性をアピールできる |
.site, .online | 汎用性があり、他と被りにくい |
.store, .shop | 商品・サービス販売との相性が良い |
希望の名前が取りやすい、意味が伝わりやすいというメリットがありますが、以下のような点に注意も必要です:
- 認知度が低く、信頼性が読者に伝わりにくい可能性
- 一部ドメインは更新費用が高い/変動しやすい
- スパムサイトに使われやすい新gTLDも存在する
用途によっては有効ですが、収益化や情報発信の信頼性を重視するなら、定番TLDの方が安心感は強いかもしれません。
「.co.jp」や「.jp」などの属性型ドメイン:法人・組織に限定される
- 「.co.jp」は、日本国内の法人企業1社につき1つのみ取得可能という厳格なルールがあります。
そのため「信頼性・本物感」が非常に高く、企業サイトに多く見られます。 - 「.jp」は、日本国内に住所があれば個人でも取得可能。
ただし「法人限定」と誤解されることもあるため、ブログ目的ならやや堅めの印象を与える可能性も。
「企業サイトっぽく見せたい」なら効果的ですが、個人ブログには少し“距離感”を生むこともあるため、狙いや印象に応じて選ぶとよいでしょう。
迷ったときは「信頼性 × 継続性 × 自分の納得感」で選ぶ
- どんなドメインでもSEO効果に大きな差はないと言われていますが、読者の印象・覚えやすさ・警戒心の有無などで違いは出ます。
- 「価格が安いから」「珍しいから」という理由だけで選ぶより、長く使えること、相手にどう見られるかを基準にすると、あとで悩みにくくなります。
5. 取得のしやすさと管理のしやすさ
どんなに理想的なドメイン名を思いついても、すでに他の人に使われていたら取得はできません。
この「取得のしやすさ」と、その後の管理のしやすさも、地味ですが見逃せないポイントです。
気に入ったドメインが使えないときの対処法

「この名前がいい」と思って検索しても、すでに使われていたり、取得はできても高額なケースもあります。
その場合に検討できる方法としては:
- 語順を入れ替える(例:blog-start → start-blog)
- ハイフンを加える(例:myblog → my-blog)
- TLDを変える(例:.com → .net や .blog)
- 造語や略語をつくる(例:blog + lab → bloglab)
ただし、ハイフンや複雑な言い回しに頼りすぎると、覚えにくくなるリスクもあるためバランスが必要です。
管理のしやすさ:サーバーとドメインは一括 or 分離?
もう一つ考えておきたいのが、ドメインをどこで取得するかという点です。
たとえば:
- サーバーと同じサービス(例:ConoHa WING や Xserver)で取得すると、管理がシンプルでSSL設定などもスムーズに連携できます。
- ムームードメイン
 やお名前.com
やお名前.com
 などドメイン専用サービスで取得すると、価格が安く自由度も高い反面、管理画面が分かれるためやや手間が増えることも。
などドメイン専用サービスで取得すると、価格が安く自由度も高い反面、管理画面が分かれるためやや手間が増えることも。
運用初心者の場合は、最初はサーバーとセットで取得しておくと迷わず進めやすいでしょう。
将来的に別サーバーに乗り換えたくなった場合も、ドメイン移管やネームサーバーの切り替えで対応は可能です。
取得後の更新忘れに注意
ドメインには必ず有効期限があります。
更新を忘れると使えなくなったり、最悪の場合は他人に取得されてしまうリスクもあるため、自動更新設定+メール通知の確認は忘れずに。
取得後も「所有し続ける責任」がある、ということを念のため意識しておくと安心です。
ドメイン取得だけで始めたい方へ
サーバーと分けて管理したい方は、
ドメイン専用サービスの利用もひとつの選択肢です。
まとめ|あとで変えられないからこそ、納得感を大切に
ドメイン選びは、ブログを始める上で最初にぶつかる「決めごと」かもしれません。
短くて覚えやすい方がいい?意味を込めた方がいい?と考え出すと、なかなか決めきれなくなることもあります。
ただ、何より大切なのは、「これで始めてみよう」と思えるかどうか。
完璧な名前ではなくても、自分が納得して、これからも使っていけそうだと感じられること。
それが、続けていくうえでの小さな自信につながります。
選んだドメインには、後から意味を見出すこともできるし、
そこに少しずつ自分らしさを積み重ねていくこともできます。
迷いながらでも、一歩踏み出せた選択には、必ず意味が生まれます。
もしまだ迷っている場合は、この記事で紹介した5つの視点を使って、
気になる名前をいくつか書き出してみるところから始めてみてください。
取得できるかどうかを調べてみるだけでも、次の行動に移りやすくなるはずです。
「これならやってみよう」と思える名前と出会えたとき、
そのときがブログのスタートラインになるかもしれません。
ドメイン名が決まったら、次は取得のステップへ
ConoHa WINGでは、対象プラン契約でドメインが2つ無料になるキャンペーンを実施中です。
サーバーと一緒に始めたい方は、ぜひチェックしてみてください。